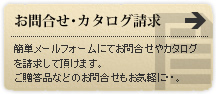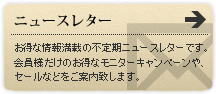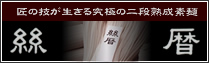トップページ > 島原そうめん史
島原そうめん史
|
そうめんの由来について |
 |
|
古くは奈良時代、唐菓子として伝来した『索餅』(麦縄)から由来したとする説が広まっています。
|
|
|
島原そうめんの由来について |
|
 |
西有家町の須川地区が発祥の地とされています。 |
|
神社由来の食物として縁起がよいとされたそうめんは、お供え物や引き出物として、また保存食として貴族の間で広く用いられました。室町時代から『索麺(さうめん)』の名で文献にみられました。『索』には縄をなう意味があり、その製法が名前の由来と思われています。 |
 |
 |
温暖な気候、雲仙山麓の良質な小麦、塩と雲仙普賢岳の伏流水などそうめん作りの条件が整っていいたため島原手延べそうめんは、麺師から麺師に受け継がれた伝統の技を今に残しています。 |
トップページ > 島原そうめん史
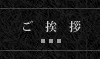
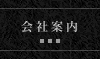
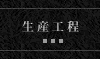
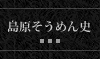
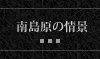
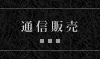
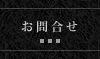
 このページの上部へ
このページの上部へ